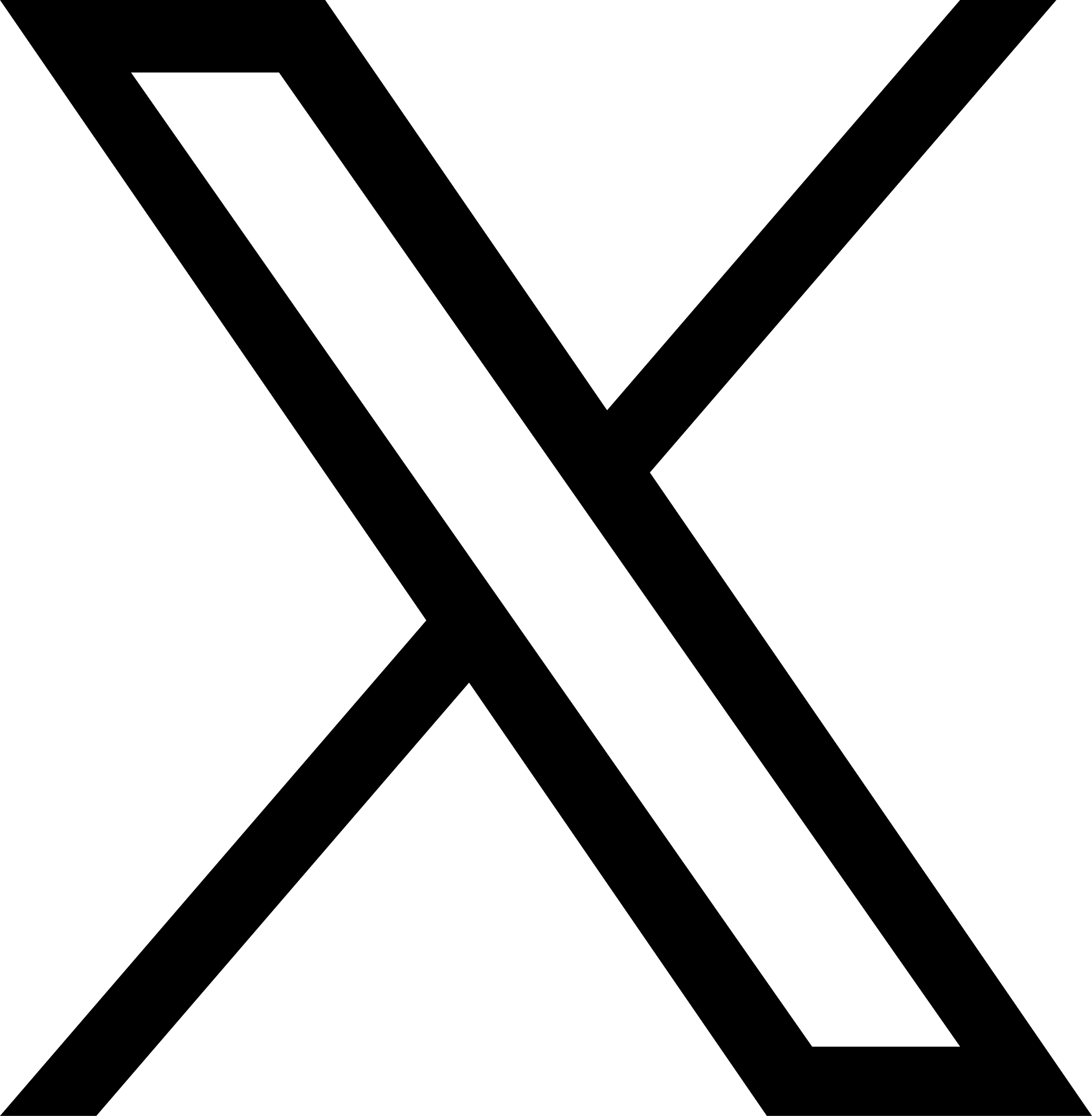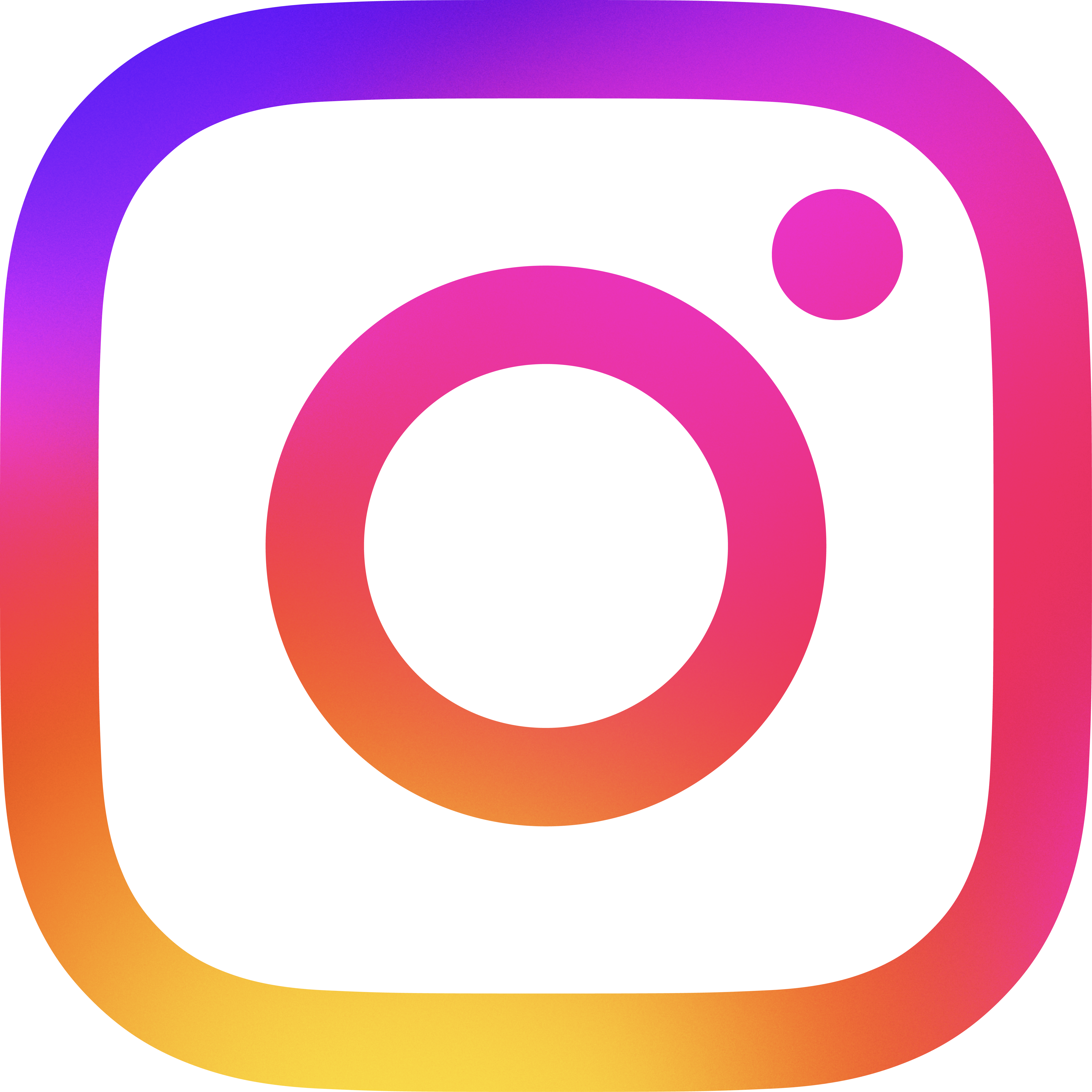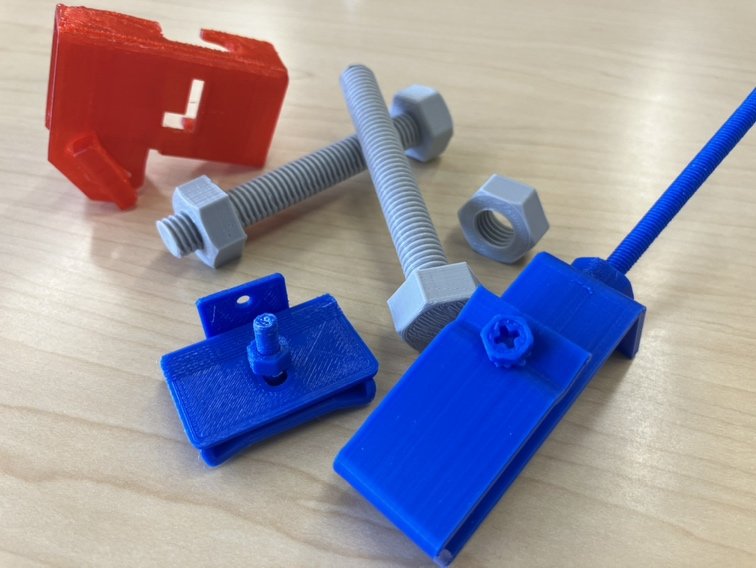建物を建築する方
新築/増築/改築/移転
建物を所有/
管理/占有する方
質問3
建築基準法第12条の定期報告※2
に規定される、
特定天井※3は
ありますか?
※2 建築基準法第12条に基づく定期報告制度により、定期点検が課せられています。
これは、建築物の所有者・管理者・占有者の義務です。
怠った場合、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
- ※3 特定天井とは、吊天井であって次のいずれにも該当するもの
- 1. 居室/廊下/人が日常立ち入る場所に設けられる(無人の工場は基準の対象外)
- 2. 6m超の高さにあって、200m²超の面積
- 3. 天井面構成部材等の単位面積重量が2kgを超えるもの
天井の耐震診断を行います。
KIRIIが加盟している日本耐震天井施工協同組合では天井耐震診断をしています。
参考サイト:日本耐震天井施工協同組合
(http://www.jacca.or.jp/)
当該診断は、定期報告制度に沿った調査とは異なります。